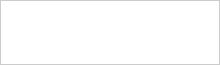―増える「責められる親」と家庭再生のヒント―
「親を責める子ども」が増える時代背景
かつては「親が子を叱る」ことが普通の時代でした。
ところが現代では、「大人はあまり子を叱るべきではない」という構図が一般化しています。
背景には、子育ての研究が進み、情報がネット(SNS)の普及によって広まったことや、社会的価値観の変化が影響していると考えられます。
・子どもを叱ると自尊心を傷つけ、脳に悪影響を与える
・子どもの人権尊重や成人年齢の引き下げ(18歳)
・男女平等、家族の関係性の変化(父の尊厳低下、母の発言力上昇など)
子育てに既存の常識が通用しなくなってきており、今の親は自分の親たちの子育てを手本にすることもままならないのです。
また、TwitterやYouTube、Instagramなどではやれ「毒親」だの「親ガチャ」だのという言葉が拡散し、若者が「親の育て方」を語るような動きも見られます。
こうした動きは一見すると若者たちのそうした発言は自立的とも捉えられます。
しかし、その裏には「親への怒り」と「自分への失望」などが複雑に絡み合っています。
子育ての比重が母親に集中すれば、そうした子どもの矛先(依存対象)は母親になってしまうことがほとんどです。
母親の立場からすれば、「どうしてそんなに責められるの?」「私は悪い親だったの?」という“被告感覚”に苦しんでしまいます。
実際、Google検索でも「親を責める子ども 心理」や「親を責める 原因」といったワードの検索数は年々上昇傾向にあります。
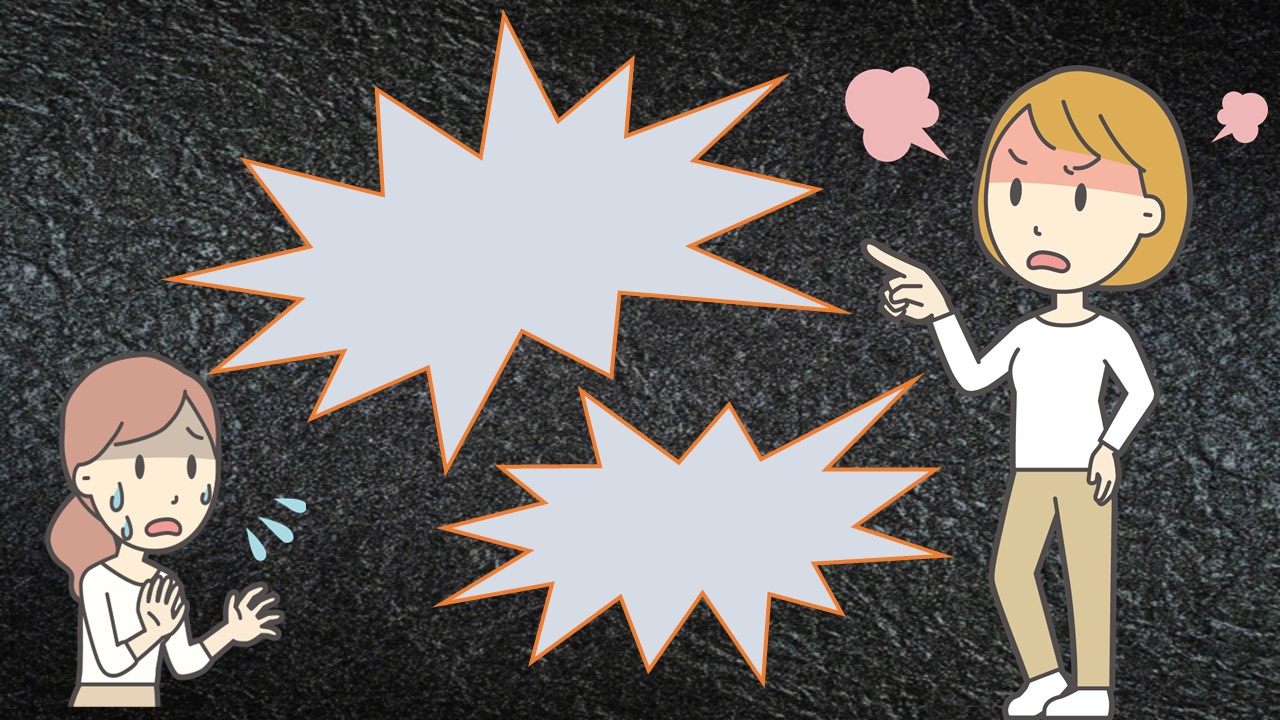
共依存のもつれが生んだモンスター
現代の家庭では、「厳しい親に反発して家を出る」よりも、「親に頼りながら責める」といったいびつな関係性が増えています。
たとえば、メンタルの不安定な娘(18歳)がいたとします。
その娘は成人しているにも関わらず経済的には母親に依存しており、それを「ママのせいでこうなった!」と攻撃的になるのです。
母親はそんな娘を心配しながら叱ることも反論することもできずに、「助けてあげたい」と「もう疲れた」という想いが交錯します。
こうした共依存関係では、当事者である母親がどんなに努力しても、娘との関係が悪化することがあります。
娘が何か思い通りに行かないことがある度に、それらは「全て母親のせい」にされてしまいます。
そのくせ自分の権利や要求だけは主張し、「私はもう大人なんだから」と、“成人”という立場を都合良く利用して母親を苦しめ続けます。
このとき親は、「私はどうしたらいいの?」と困り果て、ネット検索をして対策方法を調べたりしますが、それは“限界のサイン”でもあります。
こうした状況は単なる反抗期ではなく、長期的な心理もつれとしての親子問題が進行している悪い兆候と言えます。

「責める言葉」を正当化するZ世代
Z世代の若者の多くは、「毒親」「親ガチャ」という言葉が示すように、「親のせいで生きづらくなった」「愛されなかった」といった“被害の言葉”を使うことに抵抗がありません。
しかしそれは悪意からではなく、「自分の痛みを理解してもらいたい」という深層心理から来る表現だということをご存じでしょうか?
それを言葉の通りに受け止めてしまった親は混乱し、「そんなつもりじゃなかった」「どう応じればいいのか分からない」と自責や後悔を感じてしまいます。
社会全体が“親を反省させる言葉”に共感する風潮に傾き、親が子を見守ることしかできずに孤立してしまうケースも増えました。
結果として、「責める子」と「怯える親」という構図が固定化してしまうのです。

「責められる親」にできること
長年、「親を責める子ども」について研究してきたJECセンターが注目しているのは、この現象の裏にある心理構造です。
実は「親を責める子ども」の根底には、「自分自身を責めている子ども」が存在します。
そうした子どもたちは、親を責める(攻撃する)ことによって責任転嫁し、かろうじて自分の心の崩壊を防いでいるのです。
そのため、親が子どもに対して過度に反省の色を示したところで状況は何も変わりません。
子どもはそんなことなど求めていないのですから…。
必要なのは、客観的な視点を持つことができる第三者(専門家)と一緒に“親子の再構築”を進めることです。
JECセンターもそうした専門機関の一つとして、親御さんと娘さんの双方の心理に寄り添い、「責める言葉の裏にある悲しみ」を丁寧に解きほぐしていきます。
今、“子どもから責められて何もできない状況がつらい”と感じるのは、親が悪かったわけではありません。
この状況は子どもとの関係性を見直す機会が与えられているものとして捉えます。
権利や人権、親の責任を突き付けられ、何もできず一人で耐え忍ぶのはもう終わりにしましょう。
あなたの家庭が再び穏やかさを取り戻せるよう、JECセンターが力になると約束いたします。
そのためにも、まずは一度お電話にてご相談ください。

*JECセンターは、20年以上に及ぶパーソナリティ障害の臨床研究と回復の実績を持つ
元臨床心理士(現:施設顧問)佐藤矢市が考案した“心理休養”に基づいたサポートを提供しています。
JECセンター各種サポート
まずは無料相談をご活用ください。
Tel:0274-62-8826
受付時間9:00~20:00