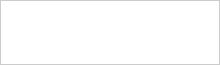皆さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
シリーズブログの第一部「小さな気づきで全てが変わる~Small changes make
a big difference」20回目になります。
パーソナリティ障害の特徴の一つに、「自分の思い」へのとらわれが強すぎるために、自分を客観的に眺めることが苦手なところがありますが、自分を客観的に眺めることのできる力を養っていくことは、確実にパーソナリティ障害の回復にもつながってきます。
今回は、そんな心の中の「落とし穴」とも形容すべき点について解説して参ります。
負のスパイラルから抜け出すには
 パーソナリティ障害者は、「憎しみ」「恨み」「怒り」といったネガティブな感情が昇華(発散)されないまま生々しく心に取りついて、自分で自分を苦しめ続けていく傾向にあります。
パーソナリティ障害者は、「憎しみ」「恨み」「怒り」といったネガティブな感情が昇華(発散)されないまま生々しく心に取りついて、自分で自分を苦しめ続けていく傾向にあります。
それが不満や愚痴、自暴自棄という形になって繰り返されていき、抜け出すための出口がなかなか見えなくなってしまいます。
例えば、話をじっくりと聞いてもらったとしても、その時はスッキリしたはずなのに、また翌日にはそんなことは忘れてしまったかのように再びネガティブな感情にとらわれてしまいます。
この無限地獄のような負のスパイラルから脱出するためには、自分を客観的に眺めることができる広い視野を身につけることが必要になります。
そうなると、視点を変え、気分を切り替えることもできるようになるのです。
見本やモデルを提示する
 その習得に一番手っ取り早いのが、客観的に眺めるやり方・コツの手本やモデルを見せてあげることです。
その習得に一番手っ取り早いのが、客観的に眺めるやり方・コツの手本やモデルを見せてあげることです。
本人が負の感情にとらわれて堂々巡りをしている時にじっくりと話を聞き、もつれた糸をほぐし、もっと大きな視野で別の物の見方を提示したり、視点を変える手ほどきを示して見せるのです。
この視点を変えることで、とらわれから脱出しやすくすることが、私たち支援者の役割でもあるのです。
例えて言うならば、泣いている子どもや、機嫌を損ねてすねている子どもをうまくあやして機嫌を直してしまう母親のスキルに似ています。
柔軟なお母さんというのは、まるで魔法でも使うように上手に子どもの気分を変えてしまっているようにも見えますが、これは子どもがとらわれていることをもっと大きな視点で見て、「たいしたことないよ!」というメッセージを送るとともに、傷ついた気持ちを巧みに慰めるということをしているだけなのです。
子どもはそんな母親からの慰めや助けを借りて、悲しみや怒りの溝から脱出することができます。
これらの作業は、親の客観的視点というモデルを、子どもに提示しているとも言えます。
子どもがすぐにそれを実行に移せなくても、そのモデルを内在化して、少しずつ習得することができるようになります。
 私たちが日々パーソナリティ障害者と接している際に心がけていることは、これらと同じことなのです。
私たちが日々パーソナリティ障害者と接している際に心がけていることは、これらと同じことなのです。
客観的視点を習得できるようになると、先に挙げた無限地獄のような堂々巡りに陥ってしまう、自分なりの落とし穴に気がつけるようになります。
落とし穴が消えてなくなるわけではありませんが、その落とし穴の場所を自覚し、避け方を習得できるようになるということは、自我の強さと呼べるものであり、パーソナリティ障害の回復の目安でもあります。